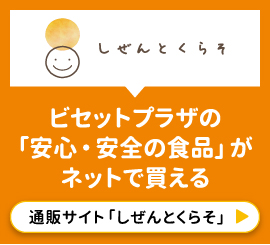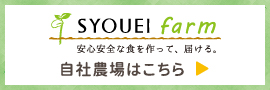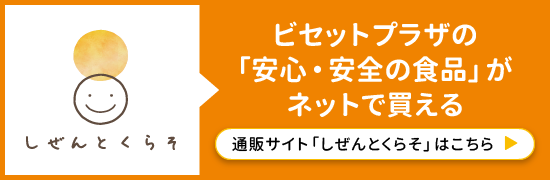玄米は完全栄養食と言われていますが何がそんなに凄いのでしょうか?
「白米より玄米の方がからだにいい」というのは誰もが一度は耳にしたことがあるのではと思われますが、なぜいいのかと聞かれるとうまく説明できないかもしれませんね?
玄米とは、籾(もみ)から*籾殻(もみがら)を取り除いた精米していないお米のことです。(*籾殻とは玄米の外側の殻のこと)
玄米には胚芽(はいが)や糠(ぬか)が残っているため栄養価が高く、玄米は完全栄養食と言われるようです。

玄米の健康パワー、実はこんなにあるんです!
1.食物繊維が豊富
生活習慣病にならないためには成人が1日に摂取したい食物繊維の量は25グラム以上が理想的だそうです。食物繊維が不足すると腸内環境が悪化して便秘に、それが原因で痔や大腸がんのリスクが高まります。
玄米150グラム(約茶碗1杯)には食物繊維がおよそ2.1グラム、白米の場合、同量でおよそ0.5グラムなので玄米ご飯は白米の4倍以上の食物繊維が摂取できることになります。
炊いた玄米には水に溶けない不溶性食物繊維がたっぷり、便通を整え、腸内環境を改善、糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急激な上昇、脂質の吸収を防いでくれます。不溶性食物繊維は腸の中で膨らみ、便のカサを増やし便を運ぶ腸の動き「ぜん動運動」を活発にし、便通を促してくれるため便秘が解消され腸内環境が整います。
2.ビタミン・ミネラルが豊富
玄米にはビタミンE、ビタミンB群、鉄、マグネシウム、カリウム、マンガン、亜鉛などが含まれています。日頃不足がちな健康維持、体調管理には欠かせないビタミンやミネラルなどの栄養素をサプリメントに頼らず補うことができます。
3.体重管理
白米と玄米に含まれるカロリーや糖質には大きな差がありませんが、玄米を主食にし、よく噛んで食べることで少量でも満腹感が得られるため体重減少につながります。
4.糖の吸収
食品に含まれる糖質は消化吸収されエネルギーになります。エネルギーになるまでのスピードはそれぞれ異なり、血糖値が上がりにくい食品のことを低GI食品と言います。玄米は白米よりもGI値が低く白米と同量の糖質を含んでいますが太りにくい性質を持っている食品と言えます。
5.γ-オリザノール(ガンマ・オリザノール)の働き
玄米特有の栄養成分、糠や胚芽に含まれるγ-オリザノールは甘いものや脂っこい食事を好まなくなる作用があると言われています。脳の中枢に作用し食欲を抑え、自然に食事の好みが変わり食べすぎを防ぐことができるようになります。
6.フェルラ酸、IP6(フィチン酸)、GABA(ギャバ)などの機能性成分が含まれています。
フェルラ酸:抗酸化作用や脳神経保護作用がある
IP6(フィチン酸):排毒・排泄作用(デトックス)、抗酸化作用、老化遅延効果がある
GABA(ギャバ):アミノ酸の一種、代謝機能を促進、高血圧を下げ、中性脂肪の増加を抑制、更年期障害の予防
他にも玄米には、人が必要とする40種類以上のビタミン・ミネラルが豊富に含まれていることから「完全栄養食」と呼ばれるようになりました。

どのように日々の食事に玄米を摂り入れたらいいの?
おすすめは主食の白米を玄米に置きかえることです。
しかしながら、最初から3食すべてを玄米に置きかえるのは抵抗があるかも…という方は、まずは1日1食から始めてみるのもいいかもしれません。最初は白米に少し混ぜ、徐々に割合を増やしていくなどブレンドして食べるという方法もよいかもしれません。玄米独特の風味が苦手と思われる方は、カレーやチャーハンなど、ごはんに味を付けてアレンジをするのもおすすめです。
玄米を炊くときは、分量を守りしっかりと浸水させてから炊き上げるのがポイントです。
食べるときは、玄米は白米よりも硬いのでよく噛んで食べることが大切です。よく噛んでゆっくりと食べる習慣をつけると早食いや食べ過ぎの防止にもつながりダイエット効果も期待できます。
玄米が完全栄養食と言われる理由がたくさんありましたね!
次回は・・・
【玄米を食べよう2!】玄米が食べにくいと感じられる方におすすめの酵素玄米ごはんと安全な玄米の選び方についてです。
お楽しみに!